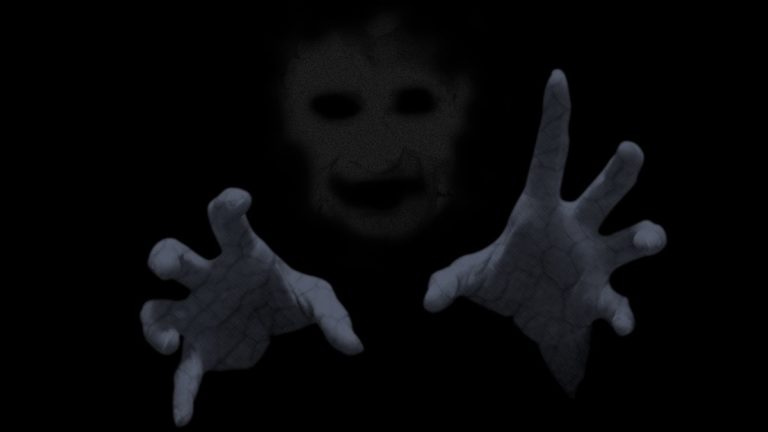呪いの種類はどんなものがあるかお調べになっている方へ。
呪いの種類はどんなものがあるかお調べになっている方へ。
呪いは古くから行われている霊力による魔術の一種です。「呪い」と言いう言葉は、日常では使われません。サイコ・サスペンス・ドラマなどで、残虐な悪魔が、「呪い殺してやる!」などと叫ぶシーンでご覧になった方がほとんどではないでしょうか。悪魔の呪いにかけられた人々は、次々に謎の死を遂げていきます。この恐ろしい「呪い」とは、いったいどんなものなのでしょう。どうして「呪い」で人々に危害を与えることができるのでしょうか。呪いにはどんな種類があるのでしょうか?
ここでは、呪いの種類について、解説していきたいと思います。
呪いには大きく分けて「過去からの呪い」と「将来への呪い」があります
呪いは古くから行われている霊力による魔術の一種です。呪いの形態は、大きく分けると「過去からの呪い」と「現在から未来に対する呪い」に分けられます。
【過去からの呪いの形態】
- 祟り・・・死んだ人が心霊化して、呪いをかけるのを「祟り」と呼びます。日本の三大祟りとしては、菅原道真、平将門、崇徳院の祟りが有名です。菅原道真や崇徳院が無くなった後、都には大きな災いが引き起こされています。その原因は、強力な怨霊のなせる業とされ、鎮魂のための神社が建てられました。将門の首塚が祀られているのも、祟りを恐れてのことです。
- 碑文などに書かれた呪文・・・エジプトの王家の墓の呪いのように、石板に呪いの呪文が書かれて、墓に侵入した者に死を与えるというような呪いです。
- 宝石類などにかけられた呪い・・・何千年あるいは何百年前の血塗られた怨念が、宝石類に宿り、持ち主にふりかかっていく呪いです。
- 魔剣と言われる刀剣類につく呪い・・・有名な名工が造った刀剣類でも、何かの原因で、名刀とならず魔剣ができてしまうことがあります。その魔剣を持つと不思議に人を切りたくなるという呪いがあります。
- 船舶などにつく呪い・・・いわゆる幽霊船です。バミューダ海域には、謎の沈没船が多く沈んでいます。霧の深い夜に、その海域を通ると幽霊船が現れます。幽霊船に乗り込むと死の呪いが待っています。
【現在から未来に対しての呪い】
- 呪術や呪文・・・恨みや憎しみから、プロの祈祷師に頼んで、悪霊の霊力などを借りて呪いをかけ、他人に害をあたえようとするもの。
- 宗教的な祈祷・・・神仏の霊力を借りて、敵対する相手を調伏しようとする場合に行います。「護摩焚き」などの方法で、導師と言われる人が一心に拝みます。
- 黒魔術的な方法・・・プロの呪術師に頼んで、呪いに効く動物や植物を加工してもらい、それを相手に気づかれないように持たせる方法。
- 人形や紙を人型に切り抜き呪う方法・・・藁人形などを使い、刺したり、切ったりして呪いを込める方法。
- 護符や呪いの札による方法・・・プロの祈祷師や導師に頼んで、護符や呪いの札を書いてもらい、部屋に貼り付ける方法。
- 呪いの手紙・・・恨む相手に差出人不明の手紙を出します。最近は、炭疽菌を模した「白い粉」が入っているものもあります。
- 呪いの電話による方法・・・恨む相手に無言電話をかける方法。ただし、番号表示になっていると、「迷惑罪」で警察のご厄介になります。
世界の国別に特色のある呪いの形態
また世界の国々にも多少の違いはありますが、いろいろな呪術や呪いがあります。
中国の蟲毒(こどく)
古代中国では、蟲毒(こどく)と言われる呪術が行われました。現在は主に中国の華南地方の少数民族に受け継がれています。動物を使うもので、犬を使うものは犬神、猫を使うものは猫神と呼んでいます。具体的な方法として、蛇やムカデなどを互いに共食いさせ、勝ち残ったものを神霊として祀ります。この動物の毒にあたると命を奪う効果があると言われています。
メソポタミアの呪いの人形
約5千年前のメソポタミアでは、憎い相手の人形を作り、心臓にあたる部分に赤色でバツ印を書き、針を突き通しました。やがて憎い相手は死ぬとされています。
エジプトのツタンカーメン王の呪いの碑文
王家の墓で見つかったピラミッドの墓の入り口の発掘の時に発見されたツタンカーメン王の呪いの碑文が有名です。ツタンカーメン王の呪いについては、後述致します。
ペルシャのゾロアスター教に由来する呪い
ペルシャのゾロアスター教に由来する呪いと言われています。白いロウで相手の像を作り、相手の髪の毛を3本、その像の中に入れます。この像に「憎しみ」の言葉を3回唱えて川に流すと、相手は水難によって死ぬと言われています。
ギリシャ・ローマの呪い
憎い相手に向かって、サタンの名において相手の不幸を願います。
フランスの呪い
ブルターニュ地方に伝わる呪いは、土や粘土で壺を作り、半獣半人の悪魔の絵を描き壺に入れます。さらに不幸を願う手紙を入れます。満月の夜、木の根元に埋めると、悪魔が壺から抜け出して相手の所へ行き願いの手紙の実行を行います。
ドイツの呪い
グリム童話の世界に伝えられた呪いの話は有名です。「白雪姫」、「シンデレラ」、「眠れる森の美女」など数々の魔女の呪いの話があります。グリム兄弟の集めたドイツの民話とされていますが、多少フランスやその他の地方の言い伝えも含まれているそうです。しかし、グリム兄弟が、グリム童話として、数々の民話をこの世に発表した功績は大きいと言えます。
イギリスの呪いの館
イギリスには古くから呪いの館(やかた)が数多くあり、幽霊が住んでいると言われています。その中でも有名な話が最近でもありました。イギリスのエセックス州にある家です。中世の時代から「魔女狩り」の刑場として使われた家なのです。過去8名の魔女が処刑されました。2004年に事情を知らないヴァネッサ・ミッチェルさんという女性が購入したところ、霊的存在が出てきて、後ろから蹴飛ばされたり、突き飛ばされたり、散々な目にあいました。売却しようとしましたが、売れないそうです。
アメリカの呪いの館
代表的な呪いの館は、ウィンチェスター・ミステリー・ハウスです。アメリカのカリフォルニア州のサンノゼにある豪華で不思議な屋敷です。ウィンチェスターは、西部開拓時代に大活躍したライフルでも有名です。ところが、ウィンチェスター家に数々の不幸が降りかかりました。霊媒師によると、ライフルで命を落とした人々の呪いだと言うのです。その呪いを消すためには、家の増築をしなければならないと言われ、年中休みなく増築し続けました。その結果、広さの総面積は2万4千平方メートルの敷地に、建物が7万2千坪(7階建て)、部屋数が160室というホテルのような家となりました。この家は、ディズニーランドのホーンテッド・マンションのモデルとも言われています。
日本の呪い
日本には古くから言霊信仰(ことだましんこう)がありました。言葉に霊が宿ると言う信仰です。言葉の霊力は強力で、日本の飛鳥時代、大和時代、奈良時代、平安時代と言霊の力が信じられていました。
聖徳太子が、中国の隋(ずい)の皇帝・煬帝(ようだい)に対して書いた手紙には、「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す」と書きました。これは、「日出ずる」で、発展を表わすからです。「日没する」で衰える意味になります。
この手紙には、裏の意味がありました。当時、隋は朝鮮半島の支配に困っていました。そこで、日本を支配下において朝鮮半島を攻略したかったのですが、聖徳太子は、中国とは対等の地位を確保したかったという意味がありました。(言霊信仰については次のコーナーで詳しくご説明します)

続いて、古代日本の呪いについてお話しいたします。