 「天照大御神」(あまてらすおおみかみ)をお調べになっている方へ。
「天照大御神」(あまてらすおおみかみ)をお調べになっている方へ。
天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、日本の最初の女神であり、「古事記」や「日本書紀」でも共通して天皇の祖であり、日本国民の総氏神(そううじがみ)とされています。

なにか重々しく厳粛な感じがしますが、本記事では、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が、どんな神様か、分かりやすく解説いたします。
天照大御神(あまてらすおおみかみ)は最古の女神です
天照大御神(あまてらすおおみかみ)のイメージは、2015年の大阪松竹座の舞台では、坂東玉三郎さんが、アマテラスを演じています。玉三郎さんの演じた神々しいアマテラスの優雅さは見る者の心を奪うほど美しい姿でした。
古い時代の映画(1959年製作「日本誕生」稲垣浩監督)では、伝説の女優・原節子さんがアマテラスを演じています。カリスマ性のある支配者としてのイメージです。
さて、神話の世界ですが、古事記や日本書紀は古代の日本にとって天皇家の権威を示すための重要な書と言えます。
古事記
「古事記は、元明天皇からの命により、太安万侶(おおのやすまろ)が、稗田阿礼(ひえだのあれ)の記憶に基づく内容を文字に直して、古事記を編纂しました。(712年)
日本書紀
「日本書記」は、天武天皇の第3皇子の舎人(とねり)親王が中心となって、太安万侶(おおのやすまろ)らと編纂を行いました。(720年)
古事記や日本書紀の目的
「古事記」や「日本書紀」はそれぞれに日本の国家統一のために天皇家を権威づける重要な書物でした。「古事記」は国内の統治を目的として編纂されました。「日本書紀」は、漢文で記され対外的に国威発揚を目的として造られました。
天照大御神の出生
「古事記」や「日本書紀」では、天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、太陽神として描かれています。また祭祀を行う巫女(みこ)としても描かれています。
父は、イザナギ(伊邪那岐神、伊邪那岐命など)です。母は、イザナミ(伊弉冉尊、伊弉弥尊)です。ただし、天照大御神(あまてらすおおみかみ)には、弟が二人います。ツクヨミ(月読命、月夜見尊)、スサノオ(建速須佐之男命、須佐之男命など)です。
夫はいませんが、スサノオと誓約した時に、五男三女神を生んでいます。太陽神に仕える巫女でもあります。
天照大御神 天岩戸(あまのいわと)のエピソード
天照大御神(あまてらすおおみかみ)の話の中に、有名な天岩戸(あまのいわと)のエピソードが出てきます。
父のイザナギが弟のスサノオを追放
父のイザナギが、弟のスサノオに海の支配を命じたところ、スサノオは、母のイザナミがいる根の国(黄泉の国)に行きたいと泣き出し、我儘を言い出しました。父のイザナギが怒ると、スサノオは暴れ出しました。そのため、山々が揺れ動き、天地は荒廃しました。
父のイザナギはしまいにスサノオを追放しました。スサノオは、母のイザナミがいる根の国に行く前に、姉の天照大御神(あまてらすおおみかみ)に会っていこうと考えました。そして、姉の住む高天原(たかまがはら)に着くと、大地に地震が起き、嵐となりました。
天岩戸に隠れる
姉の天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、いきなり現れたスサノオに驚き、「高天原を奪いに来たのか」と恐れました。そして、弟の襲撃から難を逃れるために、天岩戸(あまのいわと)と呼ばれる洞窟に隠れてしまいました。天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、太陽の神でしたので、洞窟に隠れてからは、世の中が真っ暗になってしまいました。
八百万(やおろず)の神々の作戦
世の中が暗くなり、作物が枯れ、病気が蔓延しました。困り果てた八百万(やおろず)の神々は、天岩戸の前に集まり、天照大御神(あまてらすおおみかみ)に出てきてもらう作戦を考えました。
- 最初に長鳴鳥(ながなきどり)に鳴かせました。鶏には太陽を呼ぶ力があるとされていたからです。
- 天鈿女命(あめのうずめのみこと)が、踊り始めました。それに合わせて八百万(やおろず)の神々は楽しそうに歌い手拍子を打ちました。彼女は日本最古のダンサーです。それも大胆な格好で踊りました。「古事記」によれば、大きな桶の上に乗り、おっぱいを丸出しにして、しかも下半身が見えるほど衣装をずらして踊りました。八百万(やおろず)の神々もこれには大喜びで騒ぎました。
- 天照大御神は、外の騒ぎを不思議に思って天岩戸を少し開けて、問いかけました。
- 天照大御神は、どうしてこのように楽しく騒いでいるのか聞きました。
- 「この世にあなた様よりも立派な神様が現れました」と言うと、天照大御神は身を乗り出してきました。
- そのタイミングで、思兼神(おもいかねのかみ)という神様が、天照大御神を天岩戸から引き出しました。同時に手力男命(たぢからのみこと)が天岩戸を開け放ちました。
弟のスサノオは、猛反省して姉のアマテラスと戦うつもりはないと誓約しました。そこで生まれたのが、三人の女神と五人の男神でした。全国には、この子どもたちを祀った八王子神社があります。
その後は、スサノオは出雲の国へ行き、八俣大蛇(やまたのおろち)の退治に出かけました。

天照大御神(あまてらすおおみかみ)と卑弥呼(ひみこ)の関係
天照大御神(あまてらすおおみかみ)と卑弥呼(ひみこ)は、共通点があります。
記紀に記載のない卑弥呼
「古事記」や「日本書紀」には、不思議なことに卑弥呼(ひみこ)の記載がありません。卑弥呼(ひみこ)の存在は、中国の書物である「魏志倭人伝」(ぎしわじんでん)に出てきます。魏志倭人伝は、魏の国の史書ですので、かなり信用できるものです。
しかし、魏から見ると倭国は属国であり、下に見ている書き方をしています。それでは、日本としての威厳が損なわれるということで、卑弥呼の記述は省いてしまったようです。そこで、卑弥呼の代わりに天照大御神を登場させて、天皇家の威厳をおおいに高めたものと思われます。
共通点とみられる点
- 天照大御神は、二人の弟がいます。卑弥呼にも弟がいて国政を担当しました。
- 天照大御神は、大和の国の女神です。卑弥呼は、邪馬台国の女王でした。ヤマトとヤマタイの音が似ているところがあります。
魏志倭人伝による邪馬台国の盛衰
卑弥呼(ひみこ)の没年は248年頃です。中国の歴史の書物の「魏志倭人伝」(ぎしわじんでん)には、卑弥呼の名前や邪馬台国について詳しく書かれています。
- 倭人・・・日本人を「倭人」(わじん)と呼びました。
- 倭国・・・日本は「倭国」(わこく)と呼ばれ、100以上の小国に分かれて、戦争が起きていました。
- 邪馬台国・・・女王・卑弥呼(ひみこ)が支配していました。卑弥呼は238年に「魏」に使者を送りました。魏の皇帝からは、「親魏倭王」に任じられました。
- 247年、狗奴国(くなこく)との間に紛争が起きました。
- 狗奴国(くなこく)に攻め入れられ、248年に殺されてしまいました。
- しかし、狗奴国(くなこく)の支配は、上手くいきませんでした。卑弥呼を慕うものが多く、国が治まらなかったのです。そこで、狗奴国(くなこく)の指導者は、卑弥呼の後継者の13歳の少女、壹輿(いよ)を支配者として王としました。するとようやく国が治まりました。壹輿(いよ)は、「台与」(いよ)とも表記されます。
どうして女性の天照大神が王となり政治ができたか?
天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、呪術を使う巫女のような存在だったと考えられています。実際に体現していたのは、卑弥呼(ひみこ)です。
シャーマニズムによる支配
人類が集団生活を始めてから、人類は神の支配下にあると考えられてきました。神の教えや神の思し召しを伝えるのは、巫女でした。こうした神との交流を行う人をシャーマンと呼んでいます。
科学のない社会では、皆既日食や火山の噴火、洪水、地震や津波などの自然現象が、不思議なものとして恐れられました。その答えを与えたのが、シャーマンである巫女であったのです。
そして、人々を支配するには、神のお告げが絶対のものでした。巫女は、神とのつながりを持つ特別の存在となりました。お告げが下されるとそれに基づいて政治が行われました。
天照大御神は大和朝廷のシャーマン
「古事記」や「日本書紀」で天照大御神が、天皇の祖先であるということを書き残すことで、後世、天皇が神の子孫として権威づける大切な書物でありました。天照大御神が、天皇家の祖先となった理由は、大和朝廷を支えていたたくさんの豪族たちが信奉していたのが、彼らの氏神様であった天照大御神(あまてらすおおみかみ)であったからです。
卑弥呼は神功皇后であったとする説
卑弥呼が天照大御神である説に対し、神功皇后(じんぐうこうごう)であるとする説もあります。「日本書紀」でも卑弥呼は出てきませんが、天照大御神ではなく、神功皇后(じんぐうこうごう)であるような書き方をしています。
日本書記の目的は外国に対して日本の権威を高める
- 卑弥呼を天照大御神(あまてらすおおみかみ)とした場合、卑弥呼が3世紀に存在したことから、日本建国の太古の時代(紀元前600年頃)と矛盾してしまうことが問題となりました。初代神武天皇の即位は紀元前660年頃です。
- 中国側の史書、魏志倭人伝に記載される卑弥呼は実在の人物であり、日本としては、魏の国の権威ある書を無視できませんでした。
- 「日本書紀」では、天照大御神を太古の時代の存在に書き直し、卑弥呼に該当するものとして、神功皇后の存在で書き表しました。その結果、神功皇后を天皇とせず、あくまで「皇后」の地位で書き表しました。
- 「日本書紀」の編纂者は、後世の歴史家が、神功皇后を卑弥呼・台与と同一人物と断定しないように配慮したのでした。実際、江戸時代の歴史家である国学者の本居宣長(もとおりのりなが)や後世の歴史家は、この日本書紀の編纂者の意向に沿った解釈をしています。
神功皇后の非実在説
神功皇后(じんぐうこうごう)は、第14代、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)の皇后です。非常に気丈な皇后で、夫とともに熊襲(くまそ)の征伐に随伴しました。夫が亡くなった後は、熊襲征伐を引継ぎ達成しました。その他にも海を越えて、新羅(しらぎ)の国に攻め込み、百済(くだら)や高麗(こうらい)をも服属させました。
その戦いのさなかに妊娠していましたが、第15代、応神天皇を出産しました。応神天皇が即位するまで摂政として69年間、政治を行いました。享年は100歳でした。
天照大御神はユダヤ人?
ユダヤ人の言語学者ヨセフ・アイデルバーグ氏によると、日本語とヘブライ語には、3000語以上、類似している言葉があるそうです。そのため、日本の天皇家(大和民族)とユダヤ人(古代イスラエル人)には共通の先祖があると言われています。旧約聖書によるとイスラエルには12支族がいたと記されています。そのうち10支族は世界に離散して、アジアに移動したと言われています。そのうちの一つが日本にたどり着いたとしても不思議ではありません。
共通する言葉
ヘブライ語と日本語で共通する言葉をご紹介します。
- ヘブライ語の「トル」は日本語でも「取る」
- 「アンタ」は日本語でも「あなた」
- 「ヤドゥル」は、「宿る」
- 「バレル」は、「ばれる」
- 「ヒッカケル」は、「引っかける」
天照大御神をヘブライ語にすると
ヘブライ語では、天を「シャアマ」、照らすを「テラトゥ」と言います。天照(あまてらす)は、「シャアマ・テラトゥ」となります。本当によく似ています。
また、高天原については、ヘブライ語では、「タカ・シャーアマ・ハラ」は、「タカ」という言葉は、ヘブライ語に由来するアラム語では、「台」を意味します。「シャ―アマ」が「天」、「ハラ」は、ヘブライ語で、「山」を意味します。「最高の高き台地」という意味になります。高天原のイメージにそっくりです。
相撲はイスラエルの神事であった
相撲という言葉は、ヘブライ語の似た発音で、「ヤコブ」を指す言葉であり、旧約聖書には、ヤコブと天使が相撲をしたという記述があります。そしてヤコブは勝負に勝って、「イスラエル」という名前を与えられたとされています。
相撲を始める時に、行司が「はっけよい」と声を出しますが、「はっけ」はヘブライ語で、「なげつけろ」という意味であり、「よい」は、「やっつけろ」という意味になります。
また、塩をまくという行為は、ユダヤの習慣にもあります。物をかつぐときにも、「えっさ、えっさ」と言いますが、これもヘブライ語では、「運ぶ」という意味です。
もっと興味深いのは、ソーラン節の「やーれんそーらん」という掛け声です。ヘブライ語では、「やーれん」は、「喜び唄う」という意味で、「そーらん」は、「一人で歌う者」という意味です。「ちょい」は「行進する」、「やさえ、えんやん」は、「まっすぐ進む」という意味です。
私たちがよく、「どっこいしょ」と言いますが、ヘブライ語では、「神の力で押しのける」という意味なのです。
伊勢神宮にダビデの星が刻まれている
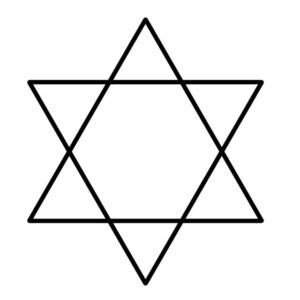 ユダヤ人の民族としての象徴として、「ダビデの星」(六芒星)と呼ばれる三角形をふたつ重ねたマークを使っています。それとまったく同じマークが、天照大御神を祀る三重県の「伊勢神宮」にあります。日本ではそれを「かごめ紋」と呼んでいます。
ユダヤ人の民族としての象徴として、「ダビデの星」(六芒星)と呼ばれる三角形をふたつ重ねたマークを使っています。それとまったく同じマークが、天照大御神を祀る三重県の「伊勢神宮」にあります。日本ではそれを「かごめ紋」と呼んでいます。
 また皇室の御紋章として、菊の花を使用していますが、これもイスラエルの首都エルサレムにある神殿の城壁に刻まれています。「かごめ」という言葉は、ヘブライ語にもあり、「カゴ・メー」と言います。「カゴ・メー」の意味は「囲む」とか「護衛する」となります。
また皇室の御紋章として、菊の花を使用していますが、これもイスラエルの首都エルサレムにある神殿の城壁に刻まれています。「かごめ」という言葉は、ヘブライ語にもあり、「カゴ・メー」と言います。「カゴ・メー」の意味は「囲む」とか「護衛する」となります。
伊勢神宮はどうやって誕生したのか?
 昔から、一生に一度は伊勢神宮にお参りにいきたいというのが人々の願いでした。「お伊勢参り」とか「お伊勢さん」と言って親しまれてきました。場所は、三重県伊勢市にあります。伊勢神宮は、天照大御神を祀る内宮と豊受大神(とゆけのおおかみ)を祀る外宮の総称です。正式名称は、単に神宮です。創立は、4世紀の初頭です。
昔から、一生に一度は伊勢神宮にお参りにいきたいというのが人々の願いでした。「お伊勢参り」とか「お伊勢さん」と言って親しまれてきました。場所は、三重県伊勢市にあります。伊勢神宮は、天照大御神を祀る内宮と豊受大神(とゆけのおおかみ)を祀る外宮の総称です。正式名称は、単に神宮です。創立は、4世紀の初頭です。

神宮を伊勢に決めた経緯
伊勢神宮を立てたのは、第11代の垂仁天皇(すいにんてんのう)です。垂仁天皇は、娘の倭姫命(やまとひめのみこと)に命じて天照大御神を祀るように指示をしました。倭姫命(やまとひめのみこと)は、天照大御神のお告げにより、伊勢に神社を作りました。これが、伊勢神宮の始まりです。
皇室と関わりが強い伊勢神宮
伊勢神宮は皇室の氏神である天照大御神(あまてらすおおみかみ)を祀っているので歴史的に皇室との関わり合いが強く、現在でも内閣総理大臣や農林水産大臣が参拝するのが慣例となっています。
伊勢神宮のご利益
伊勢神宮は、皇大神宮(こうたいじんぐう)の内宮と、豊受大神宮(とううけのおおかみぐう)の外宮に分かれています。日本の総氏神である天照大御神が祀られているのが内宮です。ここには、三種の神器のうちのひとつである八咫鏡(やたのかがみ)という銅鏡が祀られています。
伊勢神宮のお参りの順番
古神道に伝わる参拝方法・・・外宮⇒内宮⇒外宮⇒伊雑宮の順に回るのが、参拝順序とされています。
伊勢神宮のご利益
伊勢神宮にはおみくじがありません。参拝するだけで「大吉」になるというパワースポットであるからです。
- 国土を安泰にする
- 健康や幸せにする
- 交通安全
- 学業成就
- 厄除け
- 安産
- 海上安全、大漁
- 縁結び
その他なんでも願いが叶うそうです。一度はお参りしたいところです。
豊受大神(とようけおおかみ)とはどんな神様?

外宮
豊受大神は穀物の神様の娘です。天照大御神がとてもグルメであったそうなので、どうしても豊受大神を呼んで食事の世話をしてもらったようです。もし、シェフになりたい方がいらっしゃれば、是非ともお参りすることをお勧めします。
恋愛のパワースポットの月読宮(つきよみのみや)
 恋愛のパワースポットとしてご利益があるのが、外宮と内宮の中間にある月読宮(つきよみのみや)です。恋愛を成就したい方、運勢を変えたい方、子宝にめぐまれたい方、夫婦円満、良縁、縁結びのご利益があります。
恋愛のパワースポットとしてご利益があるのが、外宮と内宮の中間にある月読宮(つきよみのみや)です。恋愛を成就したい方、運勢を変えたい方、子宝にめぐまれたい方、夫婦円満、良縁、縁結びのご利益があります。
最後に
伊勢神宮の中にはたくさんのお参りする場所があり、全てがパワースポットです。運の悪い方も気持ちを切り替える意味で一度お参りしてみると良いでしょう。
全国にも天照大御神(あまてらすおおみかみ)を祀った神社がたくさんあります。お近くの神社に参拝しても同じ効果が得られます。天照大御神は、私たちにとって、とても身近な神様だということがわかります。
天照大御神とはどんな神様か?
- 天照大御神(あまてらすおおみかみ)は最古の女神です
- 天照大御神の出生
- 天照大御神 天岩戸(あまのいわと)のエピソード
- 天照大御神(あまてらすおおみかみ)と卑弥呼(ひみこ)の関係
- どうして女性の天照大神が王となり政治ができたか?
- 卑弥呼は神功皇后であったとする説
- 天照大御神はユダヤ人?
- 伊勢神宮はどうやって誕生したのか?
- 伊勢神宮のご利益

以上、最後までご覧いただき、有難うございました。



